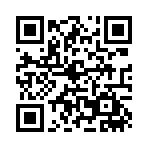2020年06月15日
讃岐漆芸美術館収蔵名品展(Ⅰ期) 作品作家紹介(そのⅨ)
讃岐漆芸美術館収蔵名品展(Ⅰ期)
作品作家紹介(そのⅨ)
現在開催中の所蔵名品展を23日(火)まで延長します。
鑑賞したいとお思いの方で、まだの方はこの週末にご来館ください。
讃岐漆芸の一つの側面(ドラマ)を語ることができます。
今回の作家作品紹介は誤って削除してしまった、そのⅤの再録です。
【作品・作家紹介(そのⅨ)】
西岡春雪「縄胎朱塗梅型丸箱」
西岡春雪の漆芸人生は同級生の1人に漆器の製造販売を営む森嘉吉商店の息子がいたことに始まる。
卒業後、同級生の誘いで森嘉吉商店に就職。漆器職人の道を歩み始める。
その頃、磯井如真らの尽力で香川県漆芸研究所が開校することとなり、1期生として入学した。
朝、職場で仕事をして、昼、研究所で学び、夕方からまた仕事をするという生活を過ごす。
この当時に漆芸研究所で教えていた磯井如真を師としている。
森嘉吉商店時代には、「堆漆塗」の座卓で、内閣総理大臣賞を受賞する。
独立後、作家活動にはいり、「縄胎」という「紐」を使う技法でボディと加飾をし、独特の朱塗りの箱を製作し、日本伝統工芸展に出品。高い評価をもらい。朝日新聞社賞などを受賞した。
作家活動もしながら、職人(伝統工芸士)としての仕事も継続し、再度、内閣総理大臣賞を受賞するなど活躍している。

山下芳広 蒟醤花器
山下芳広は、山下哲二の義父である。
磯井如真を師に蒟醤を学び、作品から日用品まで幅広く製作した。
日本伝統工芸展に数多くの作品を送り出し、親子で並んで展示されたこともある。
この花器は、下塗りに朱の漆を用い、うるみ色で上塗りをして、蒟醤で花を描いている。
研ぎ出しの加減で下塗の朱が薄っすらと透けるところがあり、現像的な趣がある。

讃岐漆芸美術館収蔵名品展
Ⅰ期展 展示作品一覧
↑ クイックしてください。別画面で表示されます。
〇 展示作家(Ⅰ期・Ⅱ期)
谷澤不二松(Ⅱ)・香川宗石(Ⅱ)・大西忠夫(Ⅱ)
安本一夫(Ⅱ)・真子実也(Ⅰ)・山田芳信(Ⅰ)
佐々木政(Ⅰ)・向井一郎(Ⅰ)・豊澤英之(Ⅰ)
佐々木達郎(Ⅰ)・国方善親(Ⅱ)・小倉敏江(Ⅰ)
東条隆一(Ⅰ)・浅賀貴宏(Ⅰ)・妹背裕(Ⅰ)
矢木佳伸(Ⅰ)・石原雅員(Ⅰ)・松原弘明(Ⅰ)
辻孝史(Ⅰ)・豊澤大志郎(Ⅱ)・香川揮山(Ⅱ) 他
〇 期間
Ⅰ期 6月5日(金)~6月21日(日)
Ⅱ期 7月24日(金)~8月16日(日)
〇 入館無料
※ 1Fのカフェコーナーをご利用いただければ幸いです。
〇 開館時間 10時~18時
◎ 会場の様子




◎讃岐漆芸美術館ワークショップ
<漆芸体験>
~お箸の漆絵付け・小皿の彫漆など、讃岐漆芸を体験できます~
お箸1客 ¥2,500-
彫漆(小皿) ¥3,000-


<金継ぎ体験>
~欠け・割れ・ひびなどした陶器・ガラス・漆器などを漆を使う金継ぎの技法で修繕します。割れ、欠け、ひび割れした陶器等をお持ちください。讃岐漆芸ならではの技法を駆使して再生します。1時間以内であれば、何個でもできます。~
1人 ¥3,000~(材料の選択により変わります)

いずれも、2人以上ですが、金継ぎ体験は1人からでも申込めます。
お電話(087-802-2010)、
もしくはメール(sanuki-urushi@mf.pikara.ne.jp)でお申込み、お問い合わせください。
【展示会・個展、案内・募集】
2021年度、当館で開催する個展やグループ展を募集しています。
漆芸以外でもOKです。
原則無料ですが、漆芸作品以外の展示は、美術館への協力として、1日あたり、階下カフェのコーヒー券1冊(11枚綴、4,500円)をご購入いただきます。
ご気軽にお問い合わせください。
【現在の展示室空き期間】
2021年5月14日(金)~
◎讃岐漆芸美術館
住所 高松市上福岡町2017-4
(車のナビゲーションは住所で設定してください)

【地図拡大】 ←クイック
電話 087-802-2010
休館中の電話 090-8286-0838(代表:多田)
メール sanuki-urushi@mf.pikara.ne.jp
作品作家紹介(そのⅨ)
現在開催中の所蔵名品展を23日(火)まで延長します。
鑑賞したいとお思いの方で、まだの方はこの週末にご来館ください。
讃岐漆芸の一つの側面(ドラマ)を語ることができます。
今回の作家作品紹介は誤って削除してしまった、そのⅤの再録です。
【作品・作家紹介(そのⅨ)】
西岡春雪「縄胎朱塗梅型丸箱」
西岡春雪の漆芸人生は同級生の1人に漆器の製造販売を営む森嘉吉商店の息子がいたことに始まる。
卒業後、同級生の誘いで森嘉吉商店に就職。漆器職人の道を歩み始める。
その頃、磯井如真らの尽力で香川県漆芸研究所が開校することとなり、1期生として入学した。
朝、職場で仕事をして、昼、研究所で学び、夕方からまた仕事をするという生活を過ごす。
この当時に漆芸研究所で教えていた磯井如真を師としている。
森嘉吉商店時代には、「堆漆塗」の座卓で、内閣総理大臣賞を受賞する。
独立後、作家活動にはいり、「縄胎」という「紐」を使う技法でボディと加飾をし、独特の朱塗りの箱を製作し、日本伝統工芸展に出品。高い評価をもらい。朝日新聞社賞などを受賞した。
作家活動もしながら、職人(伝統工芸士)としての仕事も継続し、再度、内閣総理大臣賞を受賞するなど活躍している。

山下芳広 蒟醤花器
山下芳広は、山下哲二の義父である。
磯井如真を師に蒟醤を学び、作品から日用品まで幅広く製作した。
日本伝統工芸展に数多くの作品を送り出し、親子で並んで展示されたこともある。
この花器は、下塗りに朱の漆を用い、うるみ色で上塗りをして、蒟醤で花を描いている。
研ぎ出しの加減で下塗の朱が薄っすらと透けるところがあり、現像的な趣がある。
讃岐漆芸美術館収蔵名品展
Ⅰ期展 展示作品一覧
↑ クイックしてください。別画面で表示されます。
〇 展示作家(Ⅰ期・Ⅱ期)
谷澤不二松(Ⅱ)・香川宗石(Ⅱ)・大西忠夫(Ⅱ)
安本一夫(Ⅱ)・真子実也(Ⅰ)・山田芳信(Ⅰ)
佐々木政(Ⅰ)・向井一郎(Ⅰ)・豊澤英之(Ⅰ)
佐々木達郎(Ⅰ)・国方善親(Ⅱ)・小倉敏江(Ⅰ)
東条隆一(Ⅰ)・浅賀貴宏(Ⅰ)・妹背裕(Ⅰ)
矢木佳伸(Ⅰ)・石原雅員(Ⅰ)・松原弘明(Ⅰ)
辻孝史(Ⅰ)・豊澤大志郎(Ⅱ)・香川揮山(Ⅱ) 他
〇 期間
Ⅰ期 6月5日(金)~6月21日(日)
Ⅱ期 7月24日(金)~8月16日(日)
〇 入館無料
※ 1Fのカフェコーナーをご利用いただければ幸いです。
〇 開館時間 10時~18時
◎ 会場の様子
◎讃岐漆芸美術館ワークショップ
<漆芸体験>
~お箸の漆絵付け・小皿の彫漆など、讃岐漆芸を体験できます~
お箸1客 ¥2,500-
彫漆(小皿) ¥3,000-


<金継ぎ体験>
~欠け・割れ・ひびなどした陶器・ガラス・漆器などを漆を使う金継ぎの技法で修繕します。割れ、欠け、ひび割れした陶器等をお持ちください。讃岐漆芸ならではの技法を駆使して再生します。1時間以内であれば、何個でもできます。~
1人 ¥3,000~(材料の選択により変わります)

いずれも、2人以上ですが、金継ぎ体験は1人からでも申込めます。
お電話(087-802-2010)、
もしくはメール(sanuki-urushi@mf.pikara.ne.jp)でお申込み、お問い合わせください。
【展示会・個展、案内・募集】
2021年度、当館で開催する個展やグループ展を募集しています。
漆芸以外でもOKです。
原則無料ですが、漆芸作品以外の展示は、美術館への協力として、1日あたり、階下カフェのコーヒー券1冊(11枚綴、4,500円)をご購入いただきます。
ご気軽にお問い合わせください。
【現在の展示室空き期間】
2021年5月14日(金)~
◎讃岐漆芸美術館
住所 高松市上福岡町2017-4
(車のナビゲーションは住所で設定してください)

【地図拡大】 ←クイック
電話 087-802-2010
休館中の電話 090-8286-0838(代表:多田)
メール sanuki-urushi@mf.pikara.ne.jp